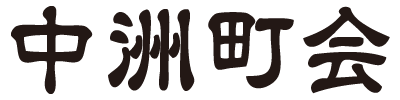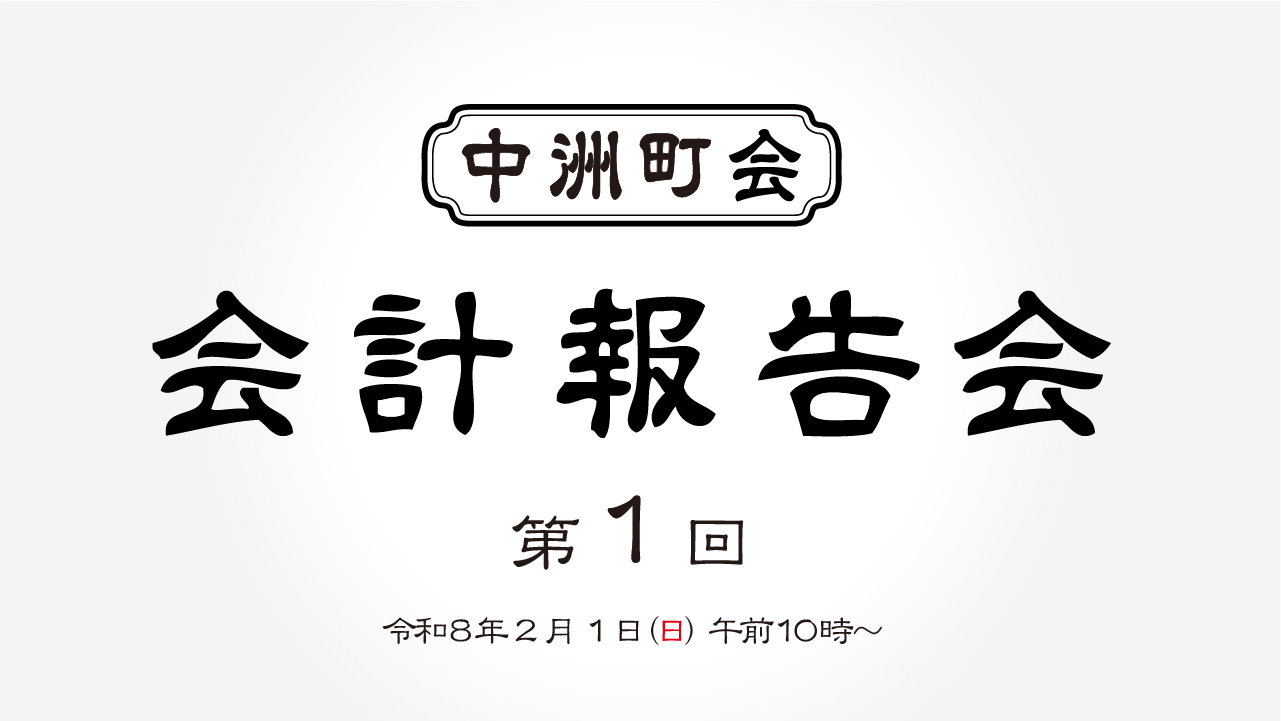中洲町会へようこそ
東京都中央区の東側、隅田川のほとりにある「中洲(なかす)」は、昔ながらの風情が今も残る、静かで落ち着いた町です。この町は、江戸の昔から川とともに歩んできた歴史があり、長く商人や職人に愛されてきました。

しかし近年、中洲の町並みは少しずつ変わり始めています。新しい建物が増え、昔ながらの家が減ってきました。そして、新しくこの町に住む人たちも増えています。若い世代の方、働く単身の方、外国の方など、いろいろな人が暮らす町へと変わってきているのです。
そうした中で、町に昔から住んでいる人たち、そして新しく引っ越してきた人たちが、気持ちよく一緒に暮らしていくためには、町会の力がますます大切になっているように思います。
昭和のころの中洲と隅田川沿いの料亭
昭和初期の中洲は、情緒豊かな町並みが広がっていました。隅田川沿いには風情ある料亭が立ち並び、夕暮れになると芸者さんたちの姿がみられ、黒塗りの高級車が列をなしていました。昭和2年(1927年)の東京日日新聞夕刊に連載された『大東京繁昌記』にて、北原白秋が「夏は短夜、紅いあかりの中洲は男橋に女橋、その男橋の上にほうふつと意気な女の影が立つ」と、中洲の夜のにぎわいと趣を美しく描いています。
こうした風景は、現在ではほとんど残っていませんが、昭和の面影を感じさせる路地や石垣など、かつての町の記憶がところどころに残っています。
変わりゆく町並みと新しい住民の姿
近年、中洲では高層マンションや新築の住宅が増え、町の景観が少しずつ変わってきました。それとともに、若い夫婦や子育て世代、単身で働く人、外国籍の方など、多様な人々が暮らす町へと姿を変えつつあります。
一方で、昔からこの町に暮らしてきた人たちの多くは高齢となり、町全体として高齢化が進んでいます。特に一人暮らしの高齢者も増えており、防災や日常の見守りなど、地域としての支え合いがますます重要になっています。

子どもたちの声と地域のにぎわい
中洲には昔から令和に至るまで、子どもたちの元気な声が響いています。

この町は中央区立有馬小学校と日本橋中学校の学区内にあり、通学路となる町なかでは、登下校の時間に子どもたちの姿がよく見られます。
町会が主催する夏祭りや防災訓練などのイベントでは、親子連れの参加が多く、町のにぎわいを感じるひとときとなっています。

特に、2年に一度の神田祭では、中洲からも神輿が出て、地域全体が一体となって盛り上がります。町会の半纏を着た子どもたちが大人たちとともに町を練り歩く様子は、今も中洲の大切な風物詩です。

町会の役割と未来へのつながり
町会では、こうした町の変化の中で、新旧の住民が気軽に関われる場づくりに取り組んでいます。掲示板や広報誌での情報共有、誰でも参加しやすいイベント、年越しを毎年決まった時期に開催し、住民同士の交流の場を設けています。
また、防災に関する活動は力を入れており、お子様から高齢者まで対応できるよう、日本橋消防署の協力も仰ぎながら、定期的な訓練を行っています。被災した時、中央区民としてどのように対応すればよいのかについて、新しく住民に加わった方々にお伝えしています。
これらの取り組みを通し、中洲住民どうしがいざという時に支え合える関係づくりを進めています。
変わる町、変わらないつながり
日本橋中洲の景観や暮らし方は、時代とともに大きく変わってきましたが、人と人とのつながりの大切さは、いつの時代も変わりません。

日々のあいさつ、小さな声かけ、助け合いの気持ち。それらが積み重なることで、この町は「住んでいてよかった」と思える場所になっていくのだと思います。

これからも日本橋中洲が、世代をこえて安心して暮らせる町として、皆さんとともに歩んでいけたらと思います。
中洲町会 会長 宮下 一雄