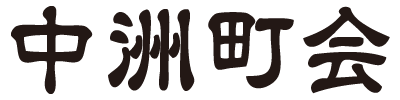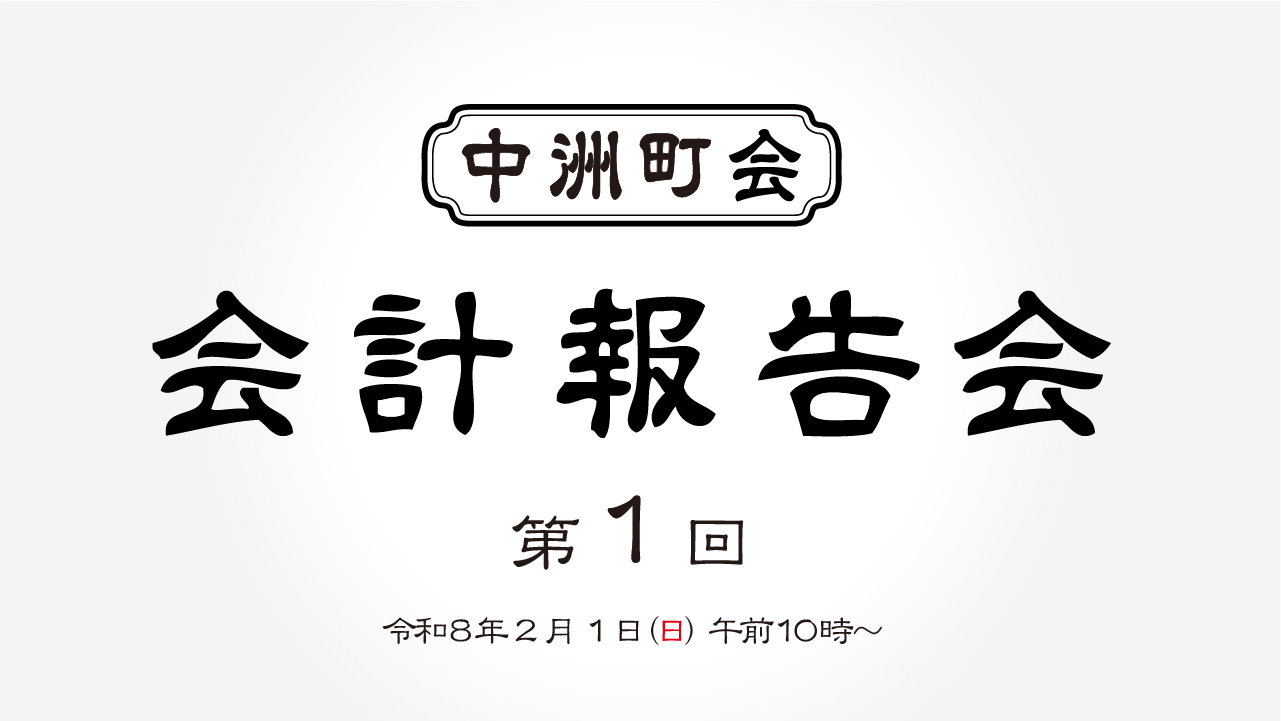令和7年3月23日(日)、中洲町会防災部主催の防災訓練が開催され、日本橋消防署の協力のもと、約40人の町会員が参加しました。今回の訓練では、災害時に備えた実践的な内容が数多く実施され、参加者たちは真剣な表情で取り組んでいました。
在宅避難の原則と避難所運営の意識
中洲地域では、災害時の避難は原則として在宅避難が基本となります。しかし、やむを得ず小学校などの避難所に行く場合でも、「やってもらう」姿勢ではなく、「自分たちで避難場所を作り上げる」意識が重要であると確認されました。地域全体で協力し、避難所の環境を整えることが求められます。

炊き出し訓練
炊き出し訓練では、非常用のご飯とレトルトカレーを使い、大鍋でお湯を沸かして温め、参加者全員で試食しました。非常時でも栄養を確保し、温かい食事を摂ることの重要性を実感する機会となりました。
防災訓練
搬送訓練
日本橋消防署の職員指導のもと、搬送訓練が実施されました。人形のダミーを用い、倒壊物に挟まれている人を発見した想定で、ジャッキを使って倒壊物を持ち上げ、安全に救助する手順を学びました。その後、担架を使用してけが人を安全な場所へ搬送する訓練も行われ、参加者は協力しながら負傷者の移動方法を習得しました。

消火訓練
消火訓練では、消火器の使い方を学びました。単に操作方法を学ぶだけでなく、「火災を発見→通報→消火器を持ってきて消火」という一連の流れをストーリー形式で実践。火災現場での冷静な対応の重要性を改めて認識しました。

心肺蘇生訓練
心肺蘇生訓練では、人形と教育用AEDを用いて、倒れている人を発見した際の対応を学びました。意識確認から、周囲の人への指示、心臓マッサージ、AEDの使用まで、一連の流れを実践しました。また、通報時には「119番にかける際に正確な住所を伝えることが重要である」との指導がありました。実際の通報時に自宅の住所を言ってしまうケースが多いため、避難先の正確な場所を伝える訓練の必要性が強調されました。

放水体験
最後に、マンションに設置されている消火ホースを使用した放水体験が行われました。初めてホースを扱う参加者も多く、適切な操作方法を学ぶ良い機会となりました。

今回の防災訓練を通じて、参加者は実践的な防災知識とスキルを身につけることができました。災害時に自分や周囲の人を守るため、日頃からの備えが重要であることを再認識する有意義な訓練となりました。令和7年3月23日(日)、中洲町会防災部主催による防災訓練が実施されました。